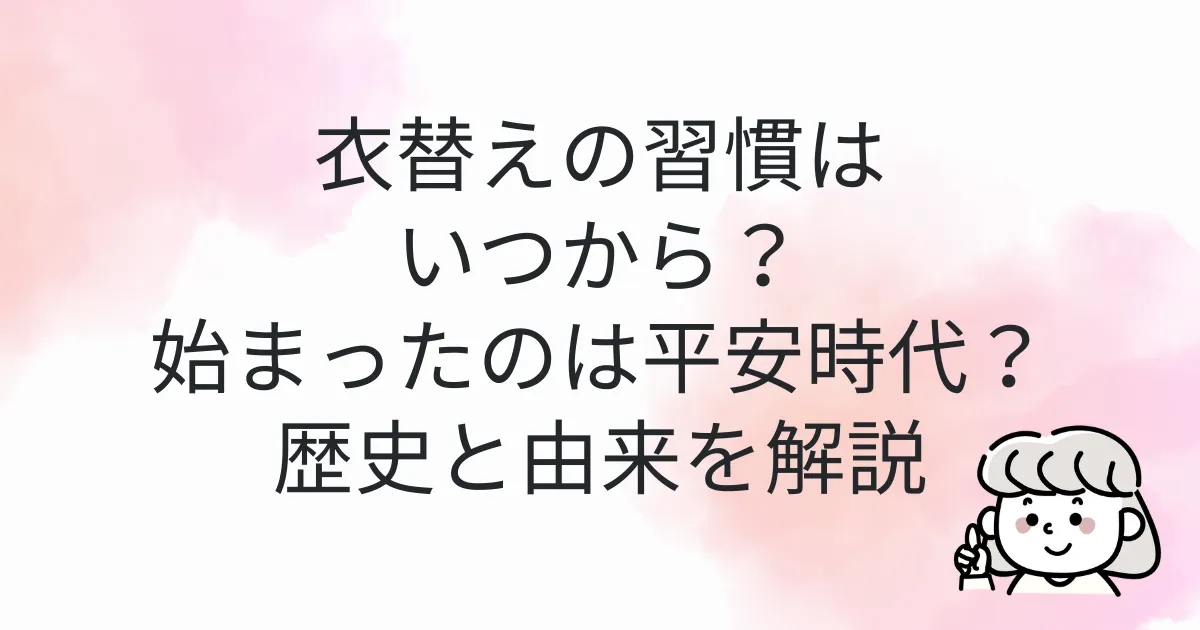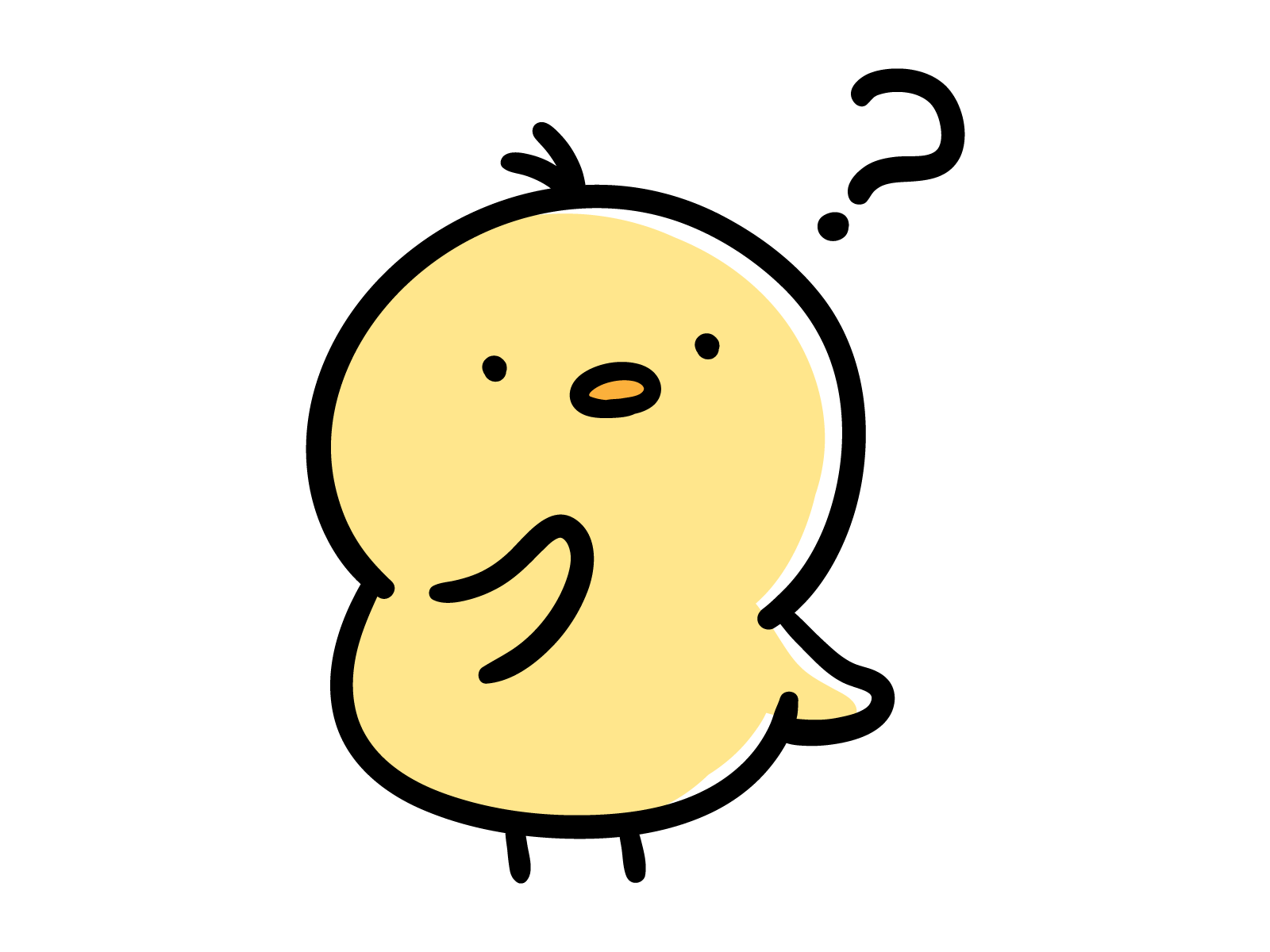
といった疑問にお答えします。
この記事では、衣替えの習慣がどのように始まり、どのように変わってきたのかを、わかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 衣替えの習慣が始まった時代と、その背景
- 平安時代の宮中行事「更衣(こうい)」が衣替えのルーツであること
- 江戸時代に衣替えが年4回の行事として定着したこと
- 明治以降の衣替えの変化と、現代の習慣の形成
- 平安時代や江戸時代の衣替えにおける色や着物の選び方のルール
それでは、詳しく説明していきますね。
衣替えの習慣はいつから?始まったのは平安時代

平安時代に始まる
衣替えは、季節の変わり目に合わせて服をかえること、この習慣は平安時代にさかのぼるんです。
平安時代には「更衣(こうい)」という行事がありました。
更衣とは、春夏秋冬の変化に合わせて衣服をかえることです。
当時の貴族たちは、季節の変化を楽しむために、それぞれの季節にふさわしい服を選んでいたんです。
この習慣は、自然と調和しながら生活するという、日本の伝統的な考え方をあらわしているんです。
時がたつにつれ、「更衣」という言葉は「衣替え」に変わり、今も続いているんですよ。
平安時代の色のルール
平安時代には、衣替えにあわせて着物の色を選ぶ「襲(かさね)の色目」というルールがありましたよ。
これは、季節や自然の風景に調和するように考えられていて、貴族たちは季節ごとにふさわしい色を着ていたんです。
たとえば、春には桜の花を思わせる薄いピンクや、若葉の緑をイメージした色が好まれました。
秋には、紅葉の赤や黄金色、冬には雪を思わせる白や寒い夜空を表現する濃い青などが使われたんですよ。
こうした色の選び方は、単に美しさを求めるだけでなく、季節の移り変わりを感じるためのものでした。
古典文学にもある衣替え
「源氏物語」や「枕草子」などの古典文学にも、衣替えに関して書いてあります。
「源氏物語」では、季節の移り変わりに合わせて衣服をかえる場面が描かれています。
春の訪れとともに明るい色の衣服を着たり、秋には重ね着をするなど、当時の貴族の生活がよくわかるんです。
また、「枕草子」では、季節ごとの美しい着物について書かれており、季節と衣服が深く結びついていることがわかりますよ。
これらの古典文学は、衣替えが単なる実用的な行為ではなく、文化的で美的な意味を持つ重要な習慣であったことを教えてくれます。
江戸時代の衣替えは年4回になる
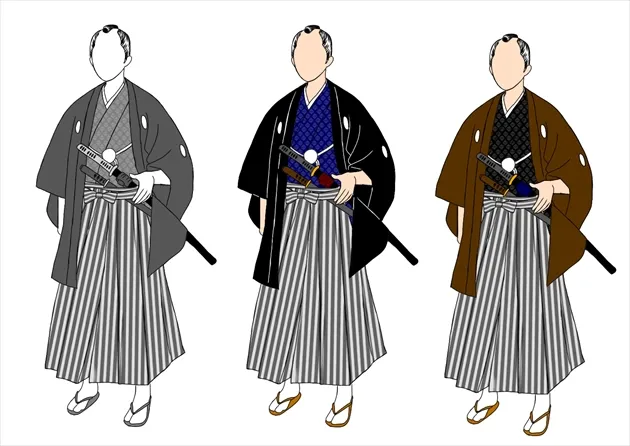
年4回の衣替え
江戸時代になると、衣替えはもっとしっかりとした習慣になりましたよ。
この時代、武士の社会では、衣替えが年4回に定められました。
季節ごとに、決まった服装をすることが求められていたんです。
このようにして、衣替えは社会的なルールとして広まっていきましたよ。
また、庶民の間でも衣替えが一般的になっていきました。
着物の種類が増えたことで、季節に応じた衣服を着るようになったんです。
これにより、衣替えは単なる季節の変わり目に合わせた行動だけでなく、着物を大切にする文化として根づいていったんですよ。
江戸時代の色のルール
江戸時代になると、色のルールは平安時代ほど厳しくはなかったです。
でも、上流階級や武士の間では、季節ごとにふさわしい色を選ぶ習慣は続いていましたよ。
たとえば、江戸時代の武士は、季節にあわせて礼服の色をかえることがありました。
春には明るい色、秋には渋めの色など、季節感を大切にする考え方があったんです。
庶民の間でも、着物の色や柄を季節に合わせて楽しむ習慣が広まっていました。
しかし、平安時代のように細かなルールがあったわけではなく、より自由に色を楽しむことができたんですよ。
明治時代以降の衣替えは変わった!洋装になったから
明治時代になると、日本の生活様式に大きな変化が訪れました。
西洋の文化が導入され、洋服が普及し始めたんです。
これに伴い、衣替えの習慣も少しずつ変わっていきましたよ。
特に学校や会社では、制服が導入され、衣替えが組織的に行われるようになったんです。
現代の衣替えは、年2回、春と秋に行うのが普通になりました。
この習慣は、明治時代に確立されたもので、今も多くの家庭や学校、職場で続いているんです。
でも、現代ではライフスタイルが多様化しているので、衣替えの方法も人それぞれになってきています。

衣替えの深い意味は、季節との共存と心のリフレッシュ
衣替えは、ただ衣服をかえるだけの行動ではないんです。
それは、季節のリズムに合わせて生活し、心をリフレッシュするための大切な習慣なんです。
自然の変化に合わせて衣服をかえることで、私たちは季節の移り変わりをより深く感じることができます。
また、衣替えはクローゼットの整理整頓の機会でもありますよ。
いらないものを処分し、新しい季節に向けて準備をすることで、心の整理も同時にできるんです。
このプロセスは、日々のストレスを軽くして、心と体をリフレッシュさせる効果があるんですよ。
まとめ~衣替えの習慣はいつから?始まったのは平安時代?歴史と由来を解説
衣替えは、平安時代から始まり、季節に合わせて服をかえる大切な習慣なんです。
昔は、季節ごとに決められた色や服装のルールがありましたが、今では自分のスタイルに合わせて楽しめるようになりましたよ。
衣替えは、自然とのつながりを感じながら、心も体もリフレッシュするための素敵な習慣ですね。
これからも大切にしていきたいですね。